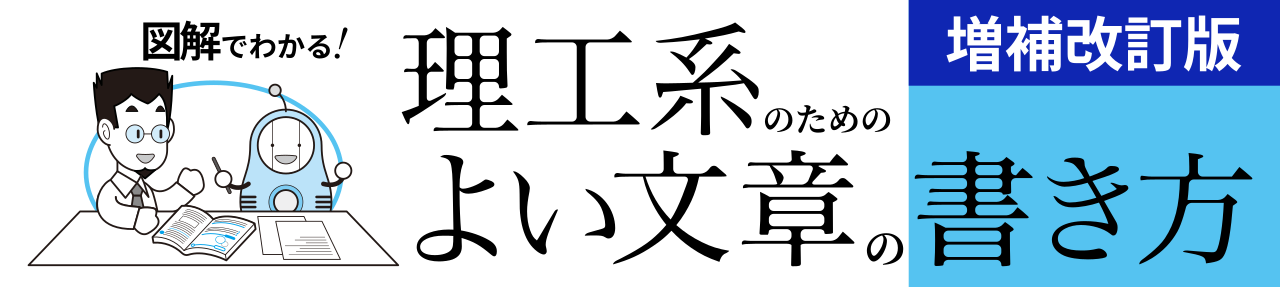人になにか行動を促すときに、
「例えば○○するなどしてみましょう」
というように、「例えば〜」とか「〜など」の言葉を添えて例を示すことがよくあります。
そしてこの言葉の裏には、実際にやってみて欲しいのは○○に限らず、それに類似した様々な行為を、自分で検討して欲しい、という気持ちが込められていることが多々あります。
ところが蓋を開けてみると、これを伝えた相手が全員、例として示したに過ぎなかったはずの○○ばかりを選択していた、なんてことがあると、相手の理解力や創造力の不足を疑い、自分が相手してきたのは言われたことをやるだけのマニュアル人間ばかりなのではないか、などと嘆きたくなるものです。
しかしこれは一概に受け手の問題ばかりにする訳にはいきません。むしろ情報の送り手側の表現に問題があった、と考えるべき場合もあるのです。
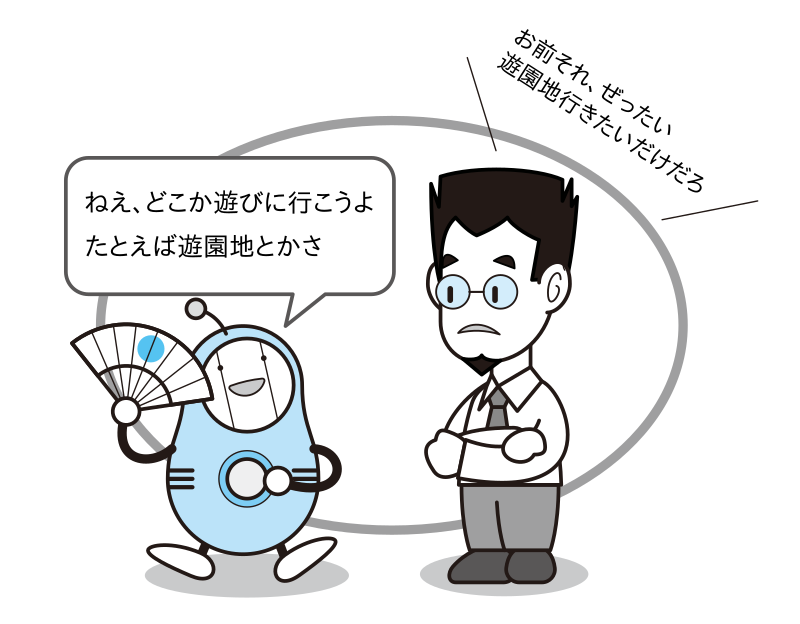
「例えば〜」や「〜など」を使って例を示す場合、それがいったいどんな特徴や性質について言及するための例なのか、それを明らかにしなければなりません。
「今日の晩御飯は中華料理がいい。例えば天津飯とか」
というように、例の近辺でその性質に言及していればまぎれはないのですが、いきなり
「今日は晩御飯は、例えば天津飯が食べたい」
と言われれば、それは天津飯しか頭にないだろう、と思われても仕方ありません。
同様の事例として、本書の「3.10 助詞の使い方を見直そう」で「単独の『など』」の使用を咎めています。例えば、
タッチディスプレイの問題点としてこれまでに、腕が疲れるなどの点が議論されてきた。
のように例が一つしか示されていないと、そこから共通する性質を読み手は推測することができないので、その例の他にどのような選択肢がありうるのか、検討するための手がかりがないのです。
複数の例が示されていたとしても、そこから意図された共通項を読み解くのが難しければ、やはり同様の困難を読み手に押しつけることになることは、本書「3.11 曖昧な表現を避ける」で説明しています。
つまり、「例えば〜」「〜など」と具体例を示すのであれば、その背後にある抽象的性質が送り手側できちんと整理されていることが必要であり、そしてそれを受け手にしっかりと伝えるべく表現しているか。それがなければ、受け手は例として示されたそれを実行せざるをえません。
実はそうした抽象的性質を送り手側は事前に練っておらず、ただ思いついた○○に「例えば〜」とつけて、さも他にもいろいろ考えてますよ、というフリをしているだけではないのか…と見透かされることのないよう、例を示すときはその抽象的性質を整理して言葉にしておくことが大事です。どうしてもその整理が難しい場合には少なくとも、複数の例を示すだけの労は惜しんではいけません。